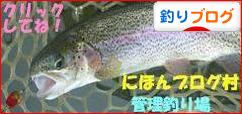2013年01月22日
つぶアン/ZANMUのカラミナ仕様
まず最初にことわっておきますが、つぶアンやZANMUを開発して制作しているムカイ・フィッシングさんは自分の最も好きなメーカーさんの一つであります。
特にOZ永井氏の大ファンであり、彼をリスペクトするとともに、大きな影響を受けてこのブログを書いていることを明記しておきます。
今回のテーマはつぶアン/ZANMU33DR/IDOフローティングタイプのチューニングです。
前々回ZANMU33DR/IDOサスペンドタイプの自分的なチューニングに関してまとめました。
それならフローティングタイプもチューニングしちゃえ、という安易な発想です。
まぁ、勝手にチューニングと言ってしまいましたが、全くたいしたことはしてません。
要は自分の使いやすいようにちょっとだけ調整するって意味合いですね。
なんとなく市販ルアーを自分用にカスタマイズするのって楽しいですからね。
誤解のないように言っておくと、前々回、今回とも自分が行っているのは決して数多く釣れるようにするための調整ではありません。
フックが絡んでしまうトラブルを出来るだけ減らして、ストレスなく釣りを続けるための調整です。
自分はフックトラブルが多いのがとにかく苦手なんです。
大物釣りにしろ数釣りにしろ、巻き心地がヘンだったり、巻いて戻ってきた時にルアーがヘンな動きをしているのを見るととガックリきてしまいます。
多少の釣果を犠牲にしてでも、ストレスなく釣りができることを目的としているのです。
フックが絡んでしまうトラブルを減らすためのチューンを行ったプラグに勝手に名前を付けました。
それが「カラミナ仕様」です。
フックをはずしたり、シンカーを付けたりする程度の変更なので、それに名前を付けるなんてバカらしいんですが気にしません。
大げさでも何でもいんです。
趣味なんて楽しんだ者勝ちなんですから。
前々回はZANMU33DR-SP、IDO-SPへの調整、今回はつぶアンF/H、ZANMU33DR-F、IDO-Fへの調整を記載しています。
カラミナの由来はなんでしょうか?
いろいろ考え、思いを込めて付けさせていただきました。
これはアフリカの片田舎にひっそりと暮らす原住民「カラミナ族」に古くから伝わる歴史ある釣法に由来するもの。
複数の釣針を変幻自在に使いながら絶対に針同士の絡まりを起こさずに芸術的に大魚を釣りあげる独特の方法。
TVのドキュメンタリー番組でそれを見て感激して付けた。
のでは決してありません。
(てゆうかカラミナ族なんてありません・・・)
昔から日焼け治療等に使われる「カラミナローション」と言う物があります。
これは酸化亜鉛の抗炎症作用を利用したマイルドな薬剤です。
効果はそれほど強くないのですが皮膚がすべすべになります。
副作用もほとんどないのでとてもいい薬だと思います。
しかし、ここではこれも関係ありません。
実は、
カ、ラ、ミ、ナは、
「カッコ良く、楽々、皆が、納得」の頭文字。
でも全くありません。
正解は・・・・・
カラミナ仕様=絡み無しよっ!
・・・・・
誠にすみません、おやじギャグをかましたかっただけです。
ゴメンなさいです。
ってことでつぶアン/ZANMUのカラミナ仕様について解説を始めます。
ZANMU33DR-SPの時に指摘した通り、フックの絡まりは圧倒的にベリーフックに多いのです。
ボトム用なら思い切ってベリーフックを外してしまってもいいと思うんですが、表層や中層の場合はやはりベリーフックの効果を捨てるわけにはいきません。
つぶアン/ZANMUのフローティングタイプが浮かんでいる姿を見ると、ほぼ同じ高さか、ベリーフックがテールフックよりも下まで垂れ下がっています。
となると真下からのアタックはベリーフックに掛かる可能性もかなり高いと考えられます。
実際にはプラグは前に進んでいるので、下からくるアタックもやや斜め後方から来る事が多いのでテールフックとベリーフックの両方が広い守備範囲で対応する形となるはずです。
表層や中層の場合、ベリーフックを外してしまうと明らかにトラウトのアタックに対応できる範囲が狭くなると思われます。
それでもスプーンやシングルフックのミニプラグと変わらないのでそのまま使うのも一つの方法かもしれません。
ただ自分的にはできれば表層と中層ではベリーフックの効果も残しながら、フックの絡まりが起こらないように調整したいところです。
ポイントとなるのはベリーフックの可動範囲です。
前々回の記事で提示したベリーフックがプラグ本体に引っ掛かるパターン、スナップあるいはリングに引っ掛かるパターンはベリーフックの可動範囲を狭めることにより防ぐ事ができると思われます。
つまりフックが動ける範囲を狭くすれば、フック自体が悪さをするところまで届かないってことです。
特に針先がプラグ本体に引っ掛かるのは、クランクではつぶアン/ZANMUに特有の絡まり方かもしれません(ミノーでは時々見られますね)。
この引っ掛かり方が自分は特に嫌いなんですよね。
繰り返すと針先が鈍ってしまう可能性が高いと思います。
外すたびに自分の指先で針先の刺さり具合を確認しなければなりません(痛いんですよ!)。
針先を爪に滑らす確認方法はイマイチ判断に自信が持てないので刺してます、はい。
実際の調整の方法を記します。
最初に前提条件を決めておきます。
フックに関してですが、使うのは基本的にVanFookのエキスパートフックです。
理由は最も手に入り易く、自分的にも使い慣れているからです。
買ったばかりのつぶアン/ZANMUに付いているのはたぶんザンムフック#8だと思われます。
太さはおそらく中軸ですね。
ザンムフックは刺さりがいいので、数釣りに適しているとてもいいフックだと思います。
ただ行きつけの釣具屋に置いてないので手に入りにくい上に、大物エリアではすぐ伸ばされちゃう事が多いんです。
なので実際のところ、つぶアン/ZANMUをしばらく使っているとベリーフックもテールフックもVanFookエキスパートフックに切り替わっている事がほとんどなのです。
ですからこの調整はどちらのフックもVanFookエキスパートフックを使う前提での話となります。
自分の場合、通常はフックを換える時はベリーもテールもSP-31BLの#6#7#8かSP41BLの#6#8を使用していました。
今回は以下の変更を加えます。
・ベリーフックのリングをシングルに換える。
・ベリーフックをクランク用のフックに変更する。
・ベリーのフックを1番小さなサイズに変更する。
以上の3点です。
まず可動範囲を狭くするにはリングを減らすのが手っ取り早いですね。
これだけでもけっこうフックがあまり暴れ回らなくなります。
シングルリングにすると当然スプーン用フックは使えないのでクランク用フックに変更となります。
クランク用に変更する事はもう一つ有利な点があるんです。
フックのアイから針先までの距離がスプーン用よりクランク用の方が短いんですよね。
他社製品は分かりませんが、VanFookエキスパートフックはそうなってます。
先程からフックの可動範囲の話をしていますが、この場合可動部のどこが一番大事かと言うと針先が動く範囲なわけです。
針先とアイが近いということはすなわち針先の可動範囲が狭くなるということなのです。
VanFookのエキスパートフックのスプーン用とクランク用だとフック自体の形状が異なっており、クランク用の方がアイと針先の距離が若干短くできているのです。
実測値を上げておきます。
手元にあるフックを手動で計ってみました。
アイの先端から針先までの直線距離です。
若干の誤差があるのはお許しください。
まずはスプーン用です。
SP31BL#5:13mm
SP41BL#6:12mm
SP11BL#7:11mm
SP21BL#7:11mm
SP31Zero#7:11mm
SP41BL#8:10.5mm
続いてクランク用です。
CK33BL#5:12mm
CK33BL#6:11mm
CK33BL#8:10mm
参考までにつぶアン/ZANMUの純正品(おそらくザンムフック#8)は11mmでした。
以上のデータから分かるのがVanFookエキスパートフックの場合、スプーン用とクランク用では同じ番手だと約1mmくらいクランク用の方がアイから針先までの距離が短いということです。
当然のことながら番手が大きいほど(フックサイズが小さいほど)アイから針先までの距離が短くなるということも言えます。
軸の太さではアイから針先までの距離は変わらない事も分かりますね。
具体的に言えばSP41BL#8からCK33BL#8に変更すると針先の可動範囲は半径にして約1mm程度、SP41BL#6からCK33BL#8の変更だと約2mm程度狭くなるわけです。

この2mmの差はかなり大きいと考えています。
ここまでやるとベリーフックの可動範囲はかなり狭く抑えられます。
ベリーフックがプラグ本体やスナップ、リングにはまず届きません。
もちろんベリーとテールのフック同士、ラインへの絡みは完全に抑えることはできません。
しかし、プラグ本体やスナップ、リングに絡まなくなればかなりトラブルを減らすことができるのではないでしょうか。

プラグ本体の上まで届かないので針先は胴体には引っかからないと思われます。

ベリーフックはテールフックのリングまで届きません。

スナップにも針先は届かないようです。
ベリーフックの可動範囲を狭くする調整を行うメリットとデメリットはどうでしょうか。
メリット
・フックの絡みをある程度減らす事ができるのが最大のメリット。
・シングルリングになるのでフック交換がしやすい。
・テールフックにトラウトが掛かった時にベリーフックでトラウトを傷つけにくくなる。
デメリット
・ベリーフックの可動範囲が狭いということは守備範囲が狭くなるということ。
・リングを減らす分フックの動きの自由度が減り、フッキングがしづらくなるかもしれない。
・フックの自由度が減るとバラシ易くなるかもしれない。
・フックサイズが小さくなるとフッキングが浅くなってバラシが増える可能性あり。
この辺のメリットデメリットをどう考えるかでしょうね。
大半のトラウトはテールフックに掛かります。
ベリーフックに掛かるのは頻度的には多くはないと思われます。
たまに掛かるベリーフックのフッキングやバラシにくさを優先的に考えるか、多少のデメリットを覚悟してでも絡みを減らすことを優先的に考えるか、がポイントですね。
それではこれから楽しい実験の時間です。
買ってきたつぶアンFをパッケージから出してそのまま湯船に浮かべてみました。
まずは斜め前から見た図。

ZANMU33DRほど前傾姿勢は深くありません。
これはおそらくリップの大きさが原因だと思われます。
ベリーフックとテールフックの高さの差が思ったよりありませんね。
次は斜め後ろから見た図。
トラウトはこの方向から来るのが多いのではないでしょうか。

ほぼ同じ高さに二つのフックがありますね。
ダブルリングなのでフックはかなり本体より下方に垂れ下がっていますね。
フックの動きの自由度は高そうではありますが、自由に動き回れるだけにいろんなところに引っかかって絡みやすいのも分かるような気がします。
かなり広い範囲を分担してカバーしている感じですね。
特に下や横からのアタックに対しては二つのフックがあるメリットは大きいのではないでしょうか。
さて泳がせてみます。
狭い湯船の中なので相変わらず動画は短いです、すみません。
しっかりテールを振っていますね。
テールが激しく振られるのでテールフックも予想以上に暴れまわります。
テールフックをダブルリングにするメリットはけっこうでかいかもしれませんね。
反面ベリーフックはそれほど動きません。
胴体の中央部は首やテールを振る場合の支点に近いので、ブレが小さいのでしょう。
よく動いて広い範囲でトラウトのアタックに臨機応変に対応するテールフック。
あまり動かずに中央部でジーっと待ち構えているベリーフック。
どうやらこの組み合わせで成り立っているようです。
となるとベリーフックの可動範囲を抑えてあまり動き回らないようにする調整は大きなデメリットにはならないのではないでしょうか。
ということでカラミナ仕様のつぶアンFを湯船に入れてみました。
斜め前から見た図です。

フックを交換前の姿勢と大きな違いはなさそうです。
ベリーフックが若干小さくなったのが分かりますね。
シングルリング化した影響でテールフックとベリーフックに少し高さの差ができています。
斜め後ろから見た図です。

これも姿勢には大きな違いはなさそうです。
こっちから見るとフックの高さの差がよりはっきりしますね。
ベリーフックの対応力が若干低下している可能性は否めません。
さて泳ぎはどう変わっているでしょうか。
見た感じではそれほど大きな変化はない気がします。
若干ベリーフックの動きがぎこちなくなった様な気もします。
トラウト目線で見るともしかしたら違うように見える可能性はありますね。
ただ大きくフッキングが不利になるような印象はこの動画からは感じませんでした。
つぶアン/ZANMU33DRのカラミナ仕様に関してまとめておきます。
サスペンドタイプを利用してボトムを狙う場合。
・ベリーフックを外してシングルフック化します。
・シンカーを貼って浮き上がらないように調整します。
フローティングタイプを利用して表層や中層を狙う場合。
・ベリーフックのリングを1個外し、シングルリング化します。
・ベリーフックを1番小さいクランク用に交換します。
まずはしばらくこれで実践してみます。
不都合があったらまた調整していきます。
実際のところはベリーフックもテールフックもラインに絡まるトラブルが一番多いんですよね。
ラインに絡まない方法があれば最高なんですけどねぇ。
特にOZ永井氏の大ファンであり、彼をリスペクトするとともに、大きな影響を受けてこのブログを書いていることを明記しておきます。
今回のテーマはつぶアン/ZANMU33DR/IDOフローティングタイプのチューニングです。
前々回ZANMU33DR/IDOサスペンドタイプの自分的なチューニングに関してまとめました。
それならフローティングタイプもチューニングしちゃえ、という安易な発想です。
まぁ、勝手にチューニングと言ってしまいましたが、全くたいしたことはしてません。
要は自分の使いやすいようにちょっとだけ調整するって意味合いですね。
なんとなく市販ルアーを自分用にカスタマイズするのって楽しいですからね。
誤解のないように言っておくと、前々回、今回とも自分が行っているのは決して数多く釣れるようにするための調整ではありません。
フックが絡んでしまうトラブルを出来るだけ減らして、ストレスなく釣りを続けるための調整です。
自分はフックトラブルが多いのがとにかく苦手なんです。
大物釣りにしろ数釣りにしろ、巻き心地がヘンだったり、巻いて戻ってきた時にルアーがヘンな動きをしているのを見るととガックリきてしまいます。
多少の釣果を犠牲にしてでも、ストレスなく釣りができることを目的としているのです。
フックが絡んでしまうトラブルを減らすためのチューンを行ったプラグに勝手に名前を付けました。
それが「カラミナ仕様」です。
フックをはずしたり、シンカーを付けたりする程度の変更なので、それに名前を付けるなんてバカらしいんですが気にしません。
大げさでも何でもいんです。
趣味なんて楽しんだ者勝ちなんですから。
前々回はZANMU33DR-SP、IDO-SPへの調整、今回はつぶアンF/H、ZANMU33DR-F、IDO-Fへの調整を記載しています。
カラミナの由来はなんでしょうか?
いろいろ考え、思いを込めて付けさせていただきました。
これはアフリカの片田舎にひっそりと暮らす原住民「カラミナ族」に古くから伝わる歴史ある釣法に由来するもの。
複数の釣針を変幻自在に使いながら絶対に針同士の絡まりを起こさずに芸術的に大魚を釣りあげる独特の方法。
TVのドキュメンタリー番組でそれを見て感激して付けた。
のでは決してありません。
(てゆうかカラミナ族なんてありません・・・)
昔から日焼け治療等に使われる「カラミナローション」と言う物があります。
これは酸化亜鉛の抗炎症作用を利用したマイルドな薬剤です。
効果はそれほど強くないのですが皮膚がすべすべになります。
副作用もほとんどないのでとてもいい薬だと思います。
しかし、ここではこれも関係ありません。
実は、
カ、ラ、ミ、ナは、
「カッコ良く、楽々、皆が、納得」の頭文字。
でも全くありません。
正解は・・・・・
カラミナ仕様=絡み無しよっ!
・・・・・
誠にすみません、おやじギャグをかましたかっただけです。
ゴメンなさいです。
ってことでつぶアン/ZANMUのカラミナ仕様について解説を始めます。
ZANMU33DR-SPの時に指摘した通り、フックの絡まりは圧倒的にベリーフックに多いのです。
ボトム用なら思い切ってベリーフックを外してしまってもいいと思うんですが、表層や中層の場合はやはりベリーフックの効果を捨てるわけにはいきません。
つぶアン/ZANMUのフローティングタイプが浮かんでいる姿を見ると、ほぼ同じ高さか、ベリーフックがテールフックよりも下まで垂れ下がっています。
となると真下からのアタックはベリーフックに掛かる可能性もかなり高いと考えられます。
実際にはプラグは前に進んでいるので、下からくるアタックもやや斜め後方から来る事が多いのでテールフックとベリーフックの両方が広い守備範囲で対応する形となるはずです。
表層や中層の場合、ベリーフックを外してしまうと明らかにトラウトのアタックに対応できる範囲が狭くなると思われます。
それでもスプーンやシングルフックのミニプラグと変わらないのでそのまま使うのも一つの方法かもしれません。
ただ自分的にはできれば表層と中層ではベリーフックの効果も残しながら、フックの絡まりが起こらないように調整したいところです。
ポイントとなるのはベリーフックの可動範囲です。
前々回の記事で提示したベリーフックがプラグ本体に引っ掛かるパターン、スナップあるいはリングに引っ掛かるパターンはベリーフックの可動範囲を狭めることにより防ぐ事ができると思われます。
つまりフックが動ける範囲を狭くすれば、フック自体が悪さをするところまで届かないってことです。
特に針先がプラグ本体に引っ掛かるのは、クランクではつぶアン/ZANMUに特有の絡まり方かもしれません(ミノーでは時々見られますね)。
この引っ掛かり方が自分は特に嫌いなんですよね。
繰り返すと針先が鈍ってしまう可能性が高いと思います。
外すたびに自分の指先で針先の刺さり具合を確認しなければなりません(痛いんですよ!)。
針先を爪に滑らす確認方法はイマイチ判断に自信が持てないので刺してます、はい。
実際の調整の方法を記します。
最初に前提条件を決めておきます。
フックに関してですが、使うのは基本的にVanFookのエキスパートフックです。
理由は最も手に入り易く、自分的にも使い慣れているからです。
買ったばかりのつぶアン/ZANMUに付いているのはたぶんザンムフック#8だと思われます。
太さはおそらく中軸ですね。
ザンムフックは刺さりがいいので、数釣りに適しているとてもいいフックだと思います。
ただ行きつけの釣具屋に置いてないので手に入りにくい上に、大物エリアではすぐ伸ばされちゃう事が多いんです。
なので実際のところ、つぶアン/ZANMUをしばらく使っているとベリーフックもテールフックもVanFookエキスパートフックに切り替わっている事がほとんどなのです。
ですからこの調整はどちらのフックもVanFookエキスパートフックを使う前提での話となります。
自分の場合、通常はフックを換える時はベリーもテールもSP-31BLの#6#7#8かSP41BLの#6#8を使用していました。
今回は以下の変更を加えます。
・ベリーフックのリングをシングルに換える。
・ベリーフックをクランク用のフックに変更する。
・ベリーのフックを1番小さなサイズに変更する。
以上の3点です。
まず可動範囲を狭くするにはリングを減らすのが手っ取り早いですね。
これだけでもけっこうフックがあまり暴れ回らなくなります。
シングルリングにすると当然スプーン用フックは使えないのでクランク用フックに変更となります。
クランク用に変更する事はもう一つ有利な点があるんです。
フックのアイから針先までの距離がスプーン用よりクランク用の方が短いんですよね。
他社製品は分かりませんが、VanFookエキスパートフックはそうなってます。
先程からフックの可動範囲の話をしていますが、この場合可動部のどこが一番大事かと言うと針先が動く範囲なわけです。
針先とアイが近いということはすなわち針先の可動範囲が狭くなるということなのです。
VanFookのエキスパートフックのスプーン用とクランク用だとフック自体の形状が異なっており、クランク用の方がアイと針先の距離が若干短くできているのです。
実測値を上げておきます。
手元にあるフックを手動で計ってみました。
アイの先端から針先までの直線距離です。
若干の誤差があるのはお許しください。
まずはスプーン用です。
SP31BL#5:13mm
SP41BL#6:12mm
SP11BL#7:11mm
SP21BL#7:11mm
SP31Zero#7:11mm
SP41BL#8:10.5mm
続いてクランク用です。
CK33BL#5:12mm
CK33BL#6:11mm
CK33BL#8:10mm
参考までにつぶアン/ZANMUの純正品(おそらくザンムフック#8)は11mmでした。
以上のデータから分かるのがVanFookエキスパートフックの場合、スプーン用とクランク用では同じ番手だと約1mmくらいクランク用の方がアイから針先までの距離が短いということです。
当然のことながら番手が大きいほど(フックサイズが小さいほど)アイから針先までの距離が短くなるということも言えます。
軸の太さではアイから針先までの距離は変わらない事も分かりますね。
具体的に言えばSP41BL#8からCK33BL#8に変更すると針先の可動範囲は半径にして約1mm程度、SP41BL#6からCK33BL#8の変更だと約2mm程度狭くなるわけです。

この2mmの差はかなり大きいと考えています。
ここまでやるとベリーフックの可動範囲はかなり狭く抑えられます。
ベリーフックがプラグ本体やスナップ、リングにはまず届きません。
もちろんベリーとテールのフック同士、ラインへの絡みは完全に抑えることはできません。
しかし、プラグ本体やスナップ、リングに絡まなくなればかなりトラブルを減らすことができるのではないでしょうか。

プラグ本体の上まで届かないので針先は胴体には引っかからないと思われます。

ベリーフックはテールフックのリングまで届きません。

スナップにも針先は届かないようです。
ベリーフックの可動範囲を狭くする調整を行うメリットとデメリットはどうでしょうか。
メリット
・フックの絡みをある程度減らす事ができるのが最大のメリット。
・シングルリングになるのでフック交換がしやすい。
・テールフックにトラウトが掛かった時にベリーフックでトラウトを傷つけにくくなる。
デメリット
・ベリーフックの可動範囲が狭いということは守備範囲が狭くなるということ。
・リングを減らす分フックの動きの自由度が減り、フッキングがしづらくなるかもしれない。
・フックの自由度が減るとバラシ易くなるかもしれない。
・フックサイズが小さくなるとフッキングが浅くなってバラシが増える可能性あり。
この辺のメリットデメリットをどう考えるかでしょうね。
大半のトラウトはテールフックに掛かります。
ベリーフックに掛かるのは頻度的には多くはないと思われます。
たまに掛かるベリーフックのフッキングやバラシにくさを優先的に考えるか、多少のデメリットを覚悟してでも絡みを減らすことを優先的に考えるか、がポイントですね。
それではこれから楽しい実験の時間です。
買ってきたつぶアンFをパッケージから出してそのまま湯船に浮かべてみました。
まずは斜め前から見た図。

ZANMU33DRほど前傾姿勢は深くありません。
これはおそらくリップの大きさが原因だと思われます。
ベリーフックとテールフックの高さの差が思ったよりありませんね。
次は斜め後ろから見た図。
トラウトはこの方向から来るのが多いのではないでしょうか。

ほぼ同じ高さに二つのフックがありますね。
ダブルリングなのでフックはかなり本体より下方に垂れ下がっていますね。
フックの動きの自由度は高そうではありますが、自由に動き回れるだけにいろんなところに引っかかって絡みやすいのも分かるような気がします。
かなり広い範囲を分担してカバーしている感じですね。
特に下や横からのアタックに対しては二つのフックがあるメリットは大きいのではないでしょうか。
さて泳がせてみます。
狭い湯船の中なので相変わらず動画は短いです、すみません。
しっかりテールを振っていますね。
テールが激しく振られるのでテールフックも予想以上に暴れまわります。
テールフックをダブルリングにするメリットはけっこうでかいかもしれませんね。
反面ベリーフックはそれほど動きません。
胴体の中央部は首やテールを振る場合の支点に近いので、ブレが小さいのでしょう。
よく動いて広い範囲でトラウトのアタックに臨機応変に対応するテールフック。
あまり動かずに中央部でジーっと待ち構えているベリーフック。
どうやらこの組み合わせで成り立っているようです。
となるとベリーフックの可動範囲を抑えてあまり動き回らないようにする調整は大きなデメリットにはならないのではないでしょうか。
ということでカラミナ仕様のつぶアンFを湯船に入れてみました。
斜め前から見た図です。

フックを交換前の姿勢と大きな違いはなさそうです。
ベリーフックが若干小さくなったのが分かりますね。
シングルリング化した影響でテールフックとベリーフックに少し高さの差ができています。
斜め後ろから見た図です。

これも姿勢には大きな違いはなさそうです。
こっちから見るとフックの高さの差がよりはっきりしますね。
ベリーフックの対応力が若干低下している可能性は否めません。
さて泳ぎはどう変わっているでしょうか。
見た感じではそれほど大きな変化はない気がします。
若干ベリーフックの動きがぎこちなくなった様な気もします。
トラウト目線で見るともしかしたら違うように見える可能性はありますね。
ただ大きくフッキングが不利になるような印象はこの動画からは感じませんでした。
つぶアン/ZANMU33DRのカラミナ仕様に関してまとめておきます。
サスペンドタイプを利用してボトムを狙う場合。
・ベリーフックを外してシングルフック化します。
・シンカーを貼って浮き上がらないように調整します。
フローティングタイプを利用して表層や中層を狙う場合。
・ベリーフックのリングを1個外し、シングルリング化します。
・ベリーフックを1番小さいクランク用に交換します。
まずはしばらくこれで実践してみます。
不都合があったらまた調整していきます。
実際のところはベリーフックもテールフックもラインに絡まるトラブルが一番多いんですよね。
ラインに絡まない方法があれば最高なんですけどねぇ。
Posted by Rose.T at 13:04│Comments(0)
│《ルアー&タックル》
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。