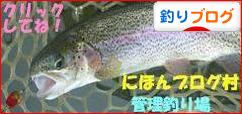2013年03月15日
自作ルアー「チョコビィ」 セカンドステップ
自作ルアーと言うのもおこがましいくらいちゃちなルアーを作り始めて、徐々にそれを改良しながらルアー製作の手順を勉強しつつある今日この頃です。
初歩のいろはも理解しないまま全くの我流で始めてみたルアー製作でしたが、最初の1個目で思いがけなくトラウトを釣る事ができて以来、完全にはまってしまいました。
このところの釣行では自作ルアーを使う機会がかなり増えてきております。
自作ルアー「チョコビィ」の作成方法や動作に関する考察をいったんH25.2/4にまとめました。
その後試行錯誤を経て、見た目も性能もややアップグレードできたと思われるので再びまとめておきます。
自分としてはヘタはヘタなりに、自作ルアーに関する技術や考え方を習得していく過程もリアルタイムにブログにアップしていこうと思っています。
今の段階の製作方法を提示します。
以前より少し手を加える部分が増えてきています。
また、ルアー作成用にいくつか道具も新たに用意してみました。
それらを紹介していきます。
まずは、ヒノキの棒を切ります。
今は25mmの長さにしています。

25mmにした一番の理由が10cmの長さの棒を切るなら25mmx4個にするのが楽だからです。
21mmで切っていくと21-21-21-37mmになって、最後だけ長くなっちゃうんです。
もう1回21mmで切ればいいのかもしれませんが、37mmから21mmを切り取るのはかなり難しいというかめんどくさいんですよね。
10cmの棒を半分にして、また半分にすれば25mm前後の同じ長さの木片が4個できます。
この方がずっと楽なので長さはあまり細かいところは気にせずに適当に進めています。
長めの方が削りすぎた時にも20mm以下になることはないのもいい点です。
次に切ったヒノキの棒を彫刻刀で削ります。
主にテール側(フック取り付け側)を削って細くします。

テールを細くした方がトラウトが食いつきやすくなるし、フックの交換が楽にできるようになります。
フックの可動域も広がるし、テールが動きやすくなり小刻みに泳いでくれるのも利点となります。
その後に今までは紙やすりや布やすりで削っていたんですが、ランダムサンダー(電動やすりがけ機)を利用することにしました。
ホームセンターで思ったより安く(3450円)で売っていたんですよね。

これを使うとやすりがけがメチャメチャ楽になりました。
ただ音がうるさいので日中限定で使っています。
ランダムサンダーでまずは荒削りをします。

スナップ側は今まで垂直に切ったまま削っていましたが、最近は斜めにカットしたりしています。
理由はルアーが浮き上がりにくくしたいのと、左右に首を振って泳いで欲しいからです。
クランクのリップをイメージしてみたわけですね。

大雑把に削るにはランダムサンダーがいいんですが、綺麗に仕上げるにはやはり自分の手で紙やすりや布やすりを当てなければなりません。
表面を滑らかになるように心がけます。

同じ形のを何個か作ってみていろんな色を試したり重さを変えて泳がせてみたり、ヒートンの向き、フックの向き、リングの数etc.テストすることになります。

ある程度納得できる形になったら水で洗い、削りカスを丹念に落とします。
そして乾燥させてから、コーティング及び色付けの作業を行います。
削りカスやゴミを完全に落とすこととしっかり乾燥させることに気を付けます。
最初にフック側とスナップ側の両方に千枚通し(穴開け用ピック)で穴を開けます。
そしてそこに楊枝をさしておきます。

楊枝を刺しておく理由はコーティングの時に穴が埋まらないようにするためと、コーティングの作業をしやすくするためです。
すぐにヒートンをはめ込んでもいいのですが、コーティングが金具にも掛かることと、ドブ漬けの作業がやりにくくなるので自分は最後にヒートンをつけるようにしています。

楊枝は普通に軽く刺しておいてもコーティングを始めるとはずれなくなります。
むしろ最後に外す時が結構大変になります。
ここまで準備ができたら下地作りに入ります。
500mlくらいビンでセルロースセメントにドブ漬けします。

最初はつけたまま半日~1日放置して置きます。
最初の1回のみ長く漬けておく理由は、しっかり滲みこんで割れにくくするためです。
2回目以降は数秒漬けてすぐに引き上げ、乾燥するために吊るしてしまいます。

木製のルアーなのでセルロースセメントにいれると普通に浮いてしまいます。
楊枝をフタで押し込む事によりルアー全体をセルロースセメント内に埋没させます。
長時間漬け込んだら、今度は乾燥させます。
乾燥用にコーラの空き箱と針金ハンガー及び洗濯バサミで乾燥箱を作成してみました。

これはなかなか使い勝手がいいんですよね。
最大で20個くらい同時に干せます。
干す時間は6-12時間です。
基本的に1日3回ドブ漬けができます。
朝仕事に行く前、仕事から帰った時、夜寝る前にそれぞれ漬けて干すことになります。
1-2回ドブ漬けしたあとでシンカーを貼ります。
スミスのチューニングシンカー7mmを1枚貼り付けます。
コーティング前にシンカーを貼らないで1-2回漬けてから貼るのには理由があります。
先に貼って半日漬けこんでみたら、何個かシンカーが剥がれて落ちてしまったんですよね。
なのでセルロースセメントのビンの底に今もシンカーが2-3枚置いたままです。
セルロースが表面とシンカーの間にしみ込んで剥がれるんでしょうね。
2回目以降のドブ漬けは数秒で引き上げるのでシンカーが剥がれることはありません。
それとシンカーを最初に貼るとその部分の木質にセルロースがしみ込まない可能性もあります。
強度的にはそれほど大きな影響はないかもしれませんが気になりました。
3-4日で計10回くらいドブ漬けするといい感じで下地が出来上がります。

半日乾燥させた後に色付けを行います。
楊枝を付けたまま色を塗ります。
最初は100円ショップの水性塗料のスプレー缶を使用しましたが、スプレーの吹き付けだと塗装が厚くなり色流れも多く見られました。
色を重ねるのもやや難しいので単色での使用となります。
今は同じく100円ショップの絵具(アクリル絵具、ガラス絵具etc.)を絵筆で塗っています。
絵筆の方が色を混ぜて作ったり、部分部分で変えたりとか融通がきくのでやり易いです。
塗りムラをなくしたい時や奇麗に仕上げたい時は同じ色の重ね塗りを行います。
別の色を重ねたい時は1色目が乾いた後にその上から塗ります。

納得できる色付けができあがったら、再び乾燥させます。
よく乾燥したら仕上げのコーティングに入ります。
下地作りの時と同じ様にセルロースセメントにドブ漬けします。
この時色流れが起こるので注意が必要です。
できればセルロース薄め液を用いて、かなり薄くてサラサラのセルロースセメントを用意したほうが色流れが起きにくくなります。
下地と同じ様に3-4日で10回程度ドブ漬けするといい感じのコーティングが出来上がります。
最後に仕上げの作業を行います。
両端の楊枝を引き抜いてそこにヒートンをはめ込みます。

楊枝を引き抜いた時に、コーティングの断端はニッパーやハサミで少し整えます。
ヒートンをはめ込んだ後にピック等で断端をヒートンの根元に押し込み奇麗に仕上げます。
そしてリングとフックを付ければ出来上がりとなります。







まだまだ試行錯誤中なので、完成された形はできていません。
最初のスプレーで色を付けただけのルアーよりはコーティングの分ちゃんとしたルアーに見えなくもないです。
カップに角度を付けたり、フック側をかなり細く削ったりとかいろいろ試しながらある程度形を決めていきたいと考えております。
リングとフックのセッティングに関しては試行錯誤の結果、ダブルリングでスプーン用フックの使用をスタンダードとしました。
試したの以下の3パターン。
①シングルリング+クランク用フック
②シングルリング+スプーン用フック
③ダブルリング+スプーン用フック
①での使用はメリットはフック交換が楽であること、フックが本体と近いこと。
デメリットはフックの自由度が低すぎてヘンな方向を向いて固定されたりする事。
クランク用フックはバリエーションが少ないので使いづらい事。
自分はスプーン用フックはサイズや太さをある程度揃えています。
例えば、太さは太軸、中軸、細軸、サイズは#4~#8というふうにです。
しかしクランク用は中軸のみサイズも#5#6#8のみしか持っていません。
気に入った太軸を使えないのが最大のデメリットかもしれません。
②のメリットはスプーン用フックが使える事が良い点です。
しばらくこの設定で使っていたんですが、最近は使わなくなりました。
一番の理由がテールのアイを横アイにせざるを得ない事です。
スプーン用フックのアイは横向きのアイなのでリング1個だとテールのアイを水平にしないと真っ直ぐにならないのです。
縦アイにするとスプーン用フックだと横を向いてしまいますからね。
横アイにもいい点があるのでしょうけれども自分はどうにもなじめませんでした。
特にゆっくり巻く傾向のプラグなのでスイムテストでも横アイだと左右の振れが安定せずにヘンな方向を向いたまま固定したりしたのが気になりました。
実際にはフックの動きはどうなっているのでしょうか。
ゆっくり巻きや特にフォーリング姿勢ではフックにかかる力のベクトルは下に向いています。
縦アイだと、アイのサークル部分の一番下がリングとの支点となります。
ほぼその1点でリングを支えるのでフックの向きは1方向に安定します。
横アイだとアイのサークル部分が水平になるのでリングの支点は180度の範囲で不安定に動いたり止まったりします。
右端までリングが行けばフックは右を向き、左端まで行けばフックは左を向きます。
縦アイと横アイだとフックの向きの安定感がかなり異なるのではないでしょうか。
ただし、速巻きだと状況は異なります。
速巻きの時はフックにかかる力のベクトルが後ろになります。
後ろ方向に引っ張られるとすれば横アイでも支点は一番後ろの1点になるのでフックは後ろ向きに安定している可能性が高いです。
後ろ向きに安定しつつ、左右の振れが大きくなると言うメリットが得られるのかもしれません。
この辺は好みの分かれるところでしょう。
トリプルフックではアイの向きはどちらでもあまり関係ないのかもしれませんが、シングルフックを使う場合はフックの向きが非常に重要なのでないかと自作ルアーを始めてから感じています。
ただセットした時に前を向く、後ろを向くだけではなく、水中で実際リーリングあるいはフォーリング、ステイングしている時にフックがどんな向きでどんな動きをしているのかがフッキングに大きな影響を与えるのは間違いないと思われます。
自分の好みはフックの向きはある程度安定していて、本体の動きに合わせて左右に引っ掛かりなく良く動くのがいいです。
あまりイレギュラーな動きはフックにはのぞみません。
自作のルアーそのものがイレギュラーな動きをしてしまいますのでフックにはそれに追従してもらいたい気持ちの方が強いです。
簡単に言っちゃえば、向きは一方向固定、動きは自由自在が理想です。
その結果、落ち着いたのが③となります。
ゆっくり巻きでも、フォーリング中、ストップ&ゴー等でも常にフックは後ろ(セッティングによっては前)を安定して向いてくれます。
メリットとしては、フックの向きが安定する事とともにフック自体の動きは自由度を増します。
可動域が広がる事もメリットですね。
バラシが少なくなります。
デメリットとしてはフック交換がしにくくなります。
そしてラインとの絡まりが増えます。
本体からフックが離れる分フッキング率が落ちる可能性があります。
不満な点が作るたびに増えていっているのが現状です。
ルアーの形や重さ、色、コーティングどれをとってもなかなか満足できません。
それでも思った以上にエリアで使って普通に釣れてくれたりするので楽しくて仕方ありません。
ああしたい、こうしたいというアイディアが次々と浮かんできます。
今後も自分なりの方法で少しずつ進化させていきたいと思います。
今のところはここまでです。
初歩のいろはも理解しないまま全くの我流で始めてみたルアー製作でしたが、最初の1個目で思いがけなくトラウトを釣る事ができて以来、完全にはまってしまいました。
このところの釣行では自作ルアーを使う機会がかなり増えてきております。
自作ルアー「チョコビィ」の作成方法や動作に関する考察をいったんH25.2/4にまとめました。
その後試行錯誤を経て、見た目も性能もややアップグレードできたと思われるので再びまとめておきます。
自分としてはヘタはヘタなりに、自作ルアーに関する技術や考え方を習得していく過程もリアルタイムにブログにアップしていこうと思っています。
今の段階の製作方法を提示します。
以前より少し手を加える部分が増えてきています。
また、ルアー作成用にいくつか道具も新たに用意してみました。
それらを紹介していきます。
まずは、ヒノキの棒を切ります。
今は25mmの長さにしています。

25mmにした一番の理由が10cmの長さの棒を切るなら25mmx4個にするのが楽だからです。
21mmで切っていくと21-21-21-37mmになって、最後だけ長くなっちゃうんです。
もう1回21mmで切ればいいのかもしれませんが、37mmから21mmを切り取るのはかなり難しいというかめんどくさいんですよね。
10cmの棒を半分にして、また半分にすれば25mm前後の同じ長さの木片が4個できます。
この方がずっと楽なので長さはあまり細かいところは気にせずに適当に進めています。
長めの方が削りすぎた時にも20mm以下になることはないのもいい点です。
次に切ったヒノキの棒を彫刻刀で削ります。
主にテール側(フック取り付け側)を削って細くします。

テールを細くした方がトラウトが食いつきやすくなるし、フックの交換が楽にできるようになります。
フックの可動域も広がるし、テールが動きやすくなり小刻みに泳いでくれるのも利点となります。
その後に今までは紙やすりや布やすりで削っていたんですが、ランダムサンダー(電動やすりがけ機)を利用することにしました。
ホームセンターで思ったより安く(3450円)で売っていたんですよね。

これを使うとやすりがけがメチャメチャ楽になりました。
ただ音がうるさいので日中限定で使っています。
ランダムサンダーでまずは荒削りをします。

スナップ側は今まで垂直に切ったまま削っていましたが、最近は斜めにカットしたりしています。
理由はルアーが浮き上がりにくくしたいのと、左右に首を振って泳いで欲しいからです。
クランクのリップをイメージしてみたわけですね。

大雑把に削るにはランダムサンダーがいいんですが、綺麗に仕上げるにはやはり自分の手で紙やすりや布やすりを当てなければなりません。
表面を滑らかになるように心がけます。

同じ形のを何個か作ってみていろんな色を試したり重さを変えて泳がせてみたり、ヒートンの向き、フックの向き、リングの数etc.テストすることになります。

ある程度納得できる形になったら水で洗い、削りカスを丹念に落とします。
そして乾燥させてから、コーティング及び色付けの作業を行います。
削りカスやゴミを完全に落とすこととしっかり乾燥させることに気を付けます。
最初にフック側とスナップ側の両方に千枚通し(穴開け用ピック)で穴を開けます。
そしてそこに楊枝をさしておきます。

楊枝を刺しておく理由はコーティングの時に穴が埋まらないようにするためと、コーティングの作業をしやすくするためです。
すぐにヒートンをはめ込んでもいいのですが、コーティングが金具にも掛かることと、ドブ漬けの作業がやりにくくなるので自分は最後にヒートンをつけるようにしています。

楊枝は普通に軽く刺しておいてもコーティングを始めるとはずれなくなります。
むしろ最後に外す時が結構大変になります。
ここまで準備ができたら下地作りに入ります。
500mlくらいビンでセルロースセメントにドブ漬けします。

最初はつけたまま半日~1日放置して置きます。
最初の1回のみ長く漬けておく理由は、しっかり滲みこんで割れにくくするためです。
2回目以降は数秒漬けてすぐに引き上げ、乾燥するために吊るしてしまいます。

木製のルアーなのでセルロースセメントにいれると普通に浮いてしまいます。
楊枝をフタで押し込む事によりルアー全体をセルロースセメント内に埋没させます。
長時間漬け込んだら、今度は乾燥させます。
乾燥用にコーラの空き箱と針金ハンガー及び洗濯バサミで乾燥箱を作成してみました。

これはなかなか使い勝手がいいんですよね。
最大で20個くらい同時に干せます。
干す時間は6-12時間です。
基本的に1日3回ドブ漬けができます。
朝仕事に行く前、仕事から帰った時、夜寝る前にそれぞれ漬けて干すことになります。
1-2回ドブ漬けしたあとでシンカーを貼ります。
スミスのチューニングシンカー7mmを1枚貼り付けます。
コーティング前にシンカーを貼らないで1-2回漬けてから貼るのには理由があります。
先に貼って半日漬けこんでみたら、何個かシンカーが剥がれて落ちてしまったんですよね。
なのでセルロースセメントのビンの底に今もシンカーが2-3枚置いたままです。
セルロースが表面とシンカーの間にしみ込んで剥がれるんでしょうね。
2回目以降のドブ漬けは数秒で引き上げるのでシンカーが剥がれることはありません。
それとシンカーを最初に貼るとその部分の木質にセルロースがしみ込まない可能性もあります。
強度的にはそれほど大きな影響はないかもしれませんが気になりました。
3-4日で計10回くらいドブ漬けするといい感じで下地が出来上がります。

半日乾燥させた後に色付けを行います。
楊枝を付けたまま色を塗ります。
最初は100円ショップの水性塗料のスプレー缶を使用しましたが、スプレーの吹き付けだと塗装が厚くなり色流れも多く見られました。
色を重ねるのもやや難しいので単色での使用となります。
今は同じく100円ショップの絵具(アクリル絵具、ガラス絵具etc.)を絵筆で塗っています。
絵筆の方が色を混ぜて作ったり、部分部分で変えたりとか融通がきくのでやり易いです。
塗りムラをなくしたい時や奇麗に仕上げたい時は同じ色の重ね塗りを行います。
別の色を重ねたい時は1色目が乾いた後にその上から塗ります。

納得できる色付けができあがったら、再び乾燥させます。
よく乾燥したら仕上げのコーティングに入ります。
下地作りの時と同じ様にセルロースセメントにドブ漬けします。
この時色流れが起こるので注意が必要です。
できればセルロース薄め液を用いて、かなり薄くてサラサラのセルロースセメントを用意したほうが色流れが起きにくくなります。
下地と同じ様に3-4日で10回程度ドブ漬けするといい感じのコーティングが出来上がります。
最後に仕上げの作業を行います。
両端の楊枝を引き抜いてそこにヒートンをはめ込みます。

楊枝を引き抜いた時に、コーティングの断端はニッパーやハサミで少し整えます。
ヒートンをはめ込んだ後にピック等で断端をヒートンの根元に押し込み奇麗に仕上げます。
そしてリングとフックを付ければ出来上がりとなります。

まだまだ試行錯誤中なので、完成された形はできていません。
最初のスプレーで色を付けただけのルアーよりはコーティングの分ちゃんとしたルアーに見えなくもないです。
カップに角度を付けたり、フック側をかなり細く削ったりとかいろいろ試しながらある程度形を決めていきたいと考えております。
リングとフックのセッティングに関しては試行錯誤の結果、ダブルリングでスプーン用フックの使用をスタンダードとしました。
試したの以下の3パターン。
①シングルリング+クランク用フック
②シングルリング+スプーン用フック
③ダブルリング+スプーン用フック
①での使用はメリットはフック交換が楽であること、フックが本体と近いこと。
デメリットはフックの自由度が低すぎてヘンな方向を向いて固定されたりする事。
クランク用フックはバリエーションが少ないので使いづらい事。
自分はスプーン用フックはサイズや太さをある程度揃えています。
例えば、太さは太軸、中軸、細軸、サイズは#4~#8というふうにです。
しかしクランク用は中軸のみサイズも#5#6#8のみしか持っていません。
気に入った太軸を使えないのが最大のデメリットかもしれません。
②のメリットはスプーン用フックが使える事が良い点です。
しばらくこの設定で使っていたんですが、最近は使わなくなりました。
一番の理由がテールのアイを横アイにせざるを得ない事です。
スプーン用フックのアイは横向きのアイなのでリング1個だとテールのアイを水平にしないと真っ直ぐにならないのです。
縦アイにするとスプーン用フックだと横を向いてしまいますからね。
横アイにもいい点があるのでしょうけれども自分はどうにもなじめませんでした。
特にゆっくり巻く傾向のプラグなのでスイムテストでも横アイだと左右の振れが安定せずにヘンな方向を向いたまま固定したりしたのが気になりました。
実際にはフックの動きはどうなっているのでしょうか。
ゆっくり巻きや特にフォーリング姿勢ではフックにかかる力のベクトルは下に向いています。
縦アイだと、アイのサークル部分の一番下がリングとの支点となります。
ほぼその1点でリングを支えるのでフックの向きは1方向に安定します。
横アイだとアイのサークル部分が水平になるのでリングの支点は180度の範囲で不安定に動いたり止まったりします。
右端までリングが行けばフックは右を向き、左端まで行けばフックは左を向きます。
縦アイと横アイだとフックの向きの安定感がかなり異なるのではないでしょうか。
ただし、速巻きだと状況は異なります。
速巻きの時はフックにかかる力のベクトルが後ろになります。
後ろ方向に引っ張られるとすれば横アイでも支点は一番後ろの1点になるのでフックは後ろ向きに安定している可能性が高いです。
後ろ向きに安定しつつ、左右の振れが大きくなると言うメリットが得られるのかもしれません。
この辺は好みの分かれるところでしょう。
トリプルフックではアイの向きはどちらでもあまり関係ないのかもしれませんが、シングルフックを使う場合はフックの向きが非常に重要なのでないかと自作ルアーを始めてから感じています。
ただセットした時に前を向く、後ろを向くだけではなく、水中で実際リーリングあるいはフォーリング、ステイングしている時にフックがどんな向きでどんな動きをしているのかがフッキングに大きな影響を与えるのは間違いないと思われます。
自分の好みはフックの向きはある程度安定していて、本体の動きに合わせて左右に引っ掛かりなく良く動くのがいいです。
あまりイレギュラーな動きはフックにはのぞみません。
自作のルアーそのものがイレギュラーな動きをしてしまいますのでフックにはそれに追従してもらいたい気持ちの方が強いです。
簡単に言っちゃえば、向きは一方向固定、動きは自由自在が理想です。
その結果、落ち着いたのが③となります。
ゆっくり巻きでも、フォーリング中、ストップ&ゴー等でも常にフックは後ろ(セッティングによっては前)を安定して向いてくれます。
メリットとしては、フックの向きが安定する事とともにフック自体の動きは自由度を増します。
可動域が広がる事もメリットですね。
バラシが少なくなります。
デメリットとしてはフック交換がしにくくなります。
そしてラインとの絡まりが増えます。
本体からフックが離れる分フッキング率が落ちる可能性があります。
不満な点が作るたびに増えていっているのが現状です。
ルアーの形や重さ、色、コーティングどれをとってもなかなか満足できません。
それでも思った以上にエリアで使って普通に釣れてくれたりするので楽しくて仕方ありません。
ああしたい、こうしたいというアイディアが次々と浮かんできます。
今後も自分なりの方法で少しずつ進化させていきたいと思います。
今のところはここまでです。
Posted by Rose.T at 19:25│Comments(2)
│《自作ルアーチョコビィ関連》
この記事へのコメント
こんばんは!
相変わらずの詳細な記事ですね!
良く分かりました。
ひとつだけ気付いたことを。
下地のセルロースを10回も漬けてるにしては木目が残ってると感じました。
それは途中でペーパー掛けしてないと読みましたがどうですか?
下地ドブ漬け乾燥後に800番程度の細かいペーパーで一度磨いてからまたドブ漬けすると仕上がりツルッツルですよ。
是非お試しあれ。
相変わらずの詳細な記事ですね!
良く分かりました。
ひとつだけ気付いたことを。
下地のセルロースを10回も漬けてるにしては木目が残ってると感じました。
それは途中でペーパー掛けしてないと読みましたがどうですか?
下地ドブ漬け乾燥後に800番程度の細かいペーパーで一度磨いてからまたドブ漬けすると仕上がりツルッツルですよ。
是非お試しあれ。
Posted by まっくす。 at 2013年03月16日 01:26
まっくす。さん、こんばんは。
前に途中の紙やすりを使ってみたんですが、イマイチ効果が分からなかったので今は使ってないんですよね。
実はこの時使っていたのが割りと薄めのセルロースセメントでした。
最近はHNKLの濃いセルロースセメントを使うようになってコーティングも厚くなりました。
800番となるとかなり細かい目ですね。
それくらいなら効果が実感できますかね。
今度試してみます。
前に途中の紙やすりを使ってみたんですが、イマイチ効果が分からなかったので今は使ってないんですよね。
実はこの時使っていたのが割りと薄めのセルロースセメントでした。
最近はHNKLの濃いセルロースセメントを使うようになってコーティングも厚くなりました。
800番となるとかなり細かい目ですね。
それくらいなら効果が実感できますかね。
今度試してみます。
Posted by Rose.T at 2013年03月17日 00:23
at 2013年03月17日 00:23
 at 2013年03月17日 00:23
at 2013年03月17日 00:23※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。